新・セルフケア
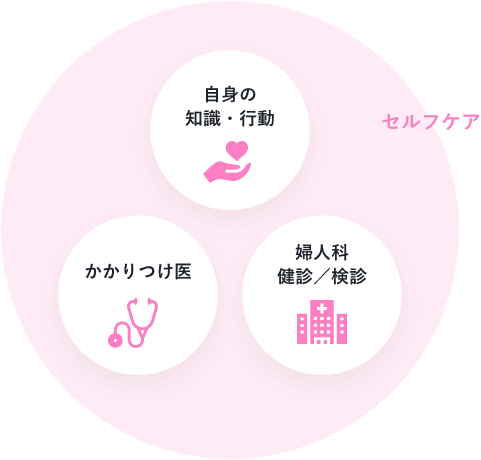
PMS・更年期症状は、
いずれも女性ホルモン(エストロゲン)が深く関わっています。
これらの諸症状とうまく付きあっていくには、
正しい知識の習得や「一般的なセルフケア」に加えて、
医療機関を利用し、自身の健康状態を把握して対処すること
が大切です。

世の中の女性たちの活躍が求められている昨今。
一方で、女性の心身は女性ホルモンの影響を大きく受け、
PMS(月経前症候群)や更年期の諸症状など一生の中で様々な女性特有の健康問題が生じます。
女性たちの持つ力を最大限発揮するためには、
こういった健康問題に正しく対処するための「ヘルスリテラシー」が重要なのではないかと考え、
大塚製薬はその現状を探るためのアンケート※を実施し、ライフステージ毎での捉え方を比較しました。
もっと日本社会が元気になるために、世の中全体で「女性の健康」について、考えてみませんか?
※ 女性の健康に関する調査 | 対象者:1. 全国の日本人女性 20-34歳 1,174名 | 2. 全国の日本人女性 35-59歳 2,826名 / 実施時期:2024年4月(インターネット調査)

女性ホルモン「エストロゲン」は、女性の守り神として様々な恩恵を与えてくれる一方で、
その変動によって、女性特有の不調が起こりやすくなります。
そんな女性ならではの不調に、どう対処しているかを聞いてみると、両年代、共に約6割もの方が医療機関を利用していませんでした。
年代での違いは、「自分で対処(セルフケア)はほとんどしないが、医療機関などを利用している人」が、
35~59歳のほうがやや多いという点です。
自身の健康状態を知るために必要な婦人科検診。
受診している人は20~34歳が5割程度であるのに対し、
35~59歳は6割が受診しており、その内訳を見ても定期的な受診者が多いことが分かりました。
ただし、受診に対する態度は、両年代共に約5割が受け身で受診していることが明らかになりました。
婦人科検診の受診理由としては、
全般的に35~59歳の方が高いものの「受診すべき年齢になったから」に次いで、
「自分の健康について知っておくべきだと思うから」や、「自分の健康に不安を感じるようになったから」など、
健康意識によるものが両年代で上位に。
また、20~34歳においては、ライフステージの変化や、両親から受診の勧めが30~59歳よりも高くなっていました。
2022年25.9% → 2024年20.3%[-5.6%]
2022年6.8% → 2024年3.5%[-3.2%]
2022年17.5% → 2024年13.6%[-3.9%]
2022年9.4% → 2024年7.3%[-2.1%]
2022年7.5% → 2024年5.4%[-2.1%]
20~34歳においては「結婚や妊娠などライフステージの変化があったから」、
35~59歳においては「職場の費用補助あるから」「テレビ・Web・ニュース等のメディアの情報を見たから」が減少。
また、数値自体は高くないものの、「配偶者・子供から受診を勧められたから」は、両年代において減少していました。
全般的に多くの項目で20~34歳の方が高い結果でしたが、
費用面や受診タイミングの他、婦人科検診の必要性を感じていないという理由が両年代で共に上位でした。
また、35~59歳においては、「女性特有の検診に抵抗があるから」や「時間がなくて受診できないから」という
理由が高くなっています。
2022年31.8% → 2024年26.3%[-5.6%]
2022年12.4% → 2024年17.2%[+4.8%]
20~34歳では、2年間での大きな変化はありませんでした。
一方、35~59歳において、必要性を感じないという人が減少し、時間的な理由で受診しない人が増加していました。
婦人科検診は、自分の健康状態や身体の変化を把握し、
体調の悪化や病気の予防につながる重要なもの。
職場や自治体の補助を積極的に活用し、婦人科検診を定期的に受診しましょう。
かかりつけ婦人科医がいない人は20~34歳で5割、35~59歳で6割弱と、
5~59歳の方がかかりつけ婦人科医がいない割合が高いという結果となりました。
ただし、かかりつけ婦人科医がいる人でも、20~34歳の方が、症状や疾患があるときにのみ受診することも分かりました。
20~34歳では、月経に関連した理由が高く、
次いで、妊娠・出産に関連した項目、女性特有のがんに関連した項目と続きました。
一方、35~59歳では、女性特有のがんに関連した項目が最も高くなりましたが、
その他、更年期を含む様々な女性特有の症状・不調に関連した様々な項目が理由としてあがるなど、
年代によってかかりつけ婦人科医がいる理由は異なりました。
2022年33.3% → 2024年24.4%[-8.8%]
2022年22.1% → 2024年15.8%[-6.3%]
2022年17.1% → 2024年21.8%[+4.7%]
2022年32.8% → 2024年26.1%[-6.7%]
20~34歳においては「妊娠・出産についての相談・検診・治療のため」が大きく減少する一方、35~59歳においては、「更年期症状に関連する婦人科系の不調の相談・検診・治療のため」が上昇。「月経・更年期・女性特有のがん以外の症状・不調の相談・検診・治療のため」という回答は、両年代で共に減少していました。
「かかりつけ婦人科医をどう探したらいいか分からないから」という理由が最も高く
「婦人科が通いやすい場所にないから」「必要性について考えたことがないから」といった理由も両年代で共通していました。
年代別で異なるのは、20~34歳では「婦人科医に行く時間がないから」という理由が高く
35~59歳では、「定期的に健康診断を受けているから」という理由が高い点です。
2022年20.6% → 2024年16.0%[-4.6%]
両年代において各項目で全般的に大きな変化がない中、
20~34歳において、「かかりつけ医の必要性について考えたことがないから」という理由のみ、減少していました。
婦人科・婦人科医へのイメージは、両年代共に、「自分の身体のことを知るために必要だと思う」
「もっと身近であって欲しい」「相談できて頼りになる」など重要だと感じているようです。
年代別で異なるのは、20~34歳は「婦人科受診は妊娠・出産の時以外は関係ないと思う」
「どのような時に婦人科を受診するのかわからない」といった、
婦人科を特定の時以外にどう利用していいか分からないという理由が高く、
35~59歳は「婦人科を受診することに抵抗を感じる」「婦人科を受診することは恥ずかしいと思う」など
心理的な理由が高くなる傾向でした。
2022年76.3% → 2024年71.7%[-4.6%]
2022年87.7% → 2024年83.2%[-4.5%]
2022年36.3% → 2024年32.9%[-3.4%]
2022年89.8% → 2024年87.0%[-2.8%]
2022年88.6% → 2024年86.6%[-2.0%]
「婦人科はもっと身近であって欲しいと思う」という回答は両年代で減少していました。
年代別で異なるのは、20~34歳においては「自分の身体について相談できて、頼りになると思う」が減少し、
30~59歳においては、「受診することは恥ずかしいと思う」、「自分の身体のことを知るために必要だと思う」という回答が減少していました。
女性の健康管理に取り組む上では、
一般的なセルフケア(食生活・運動・サプリメント利用等)に加えて、
“専門家による健康状態を把握”によって、体調の悪化や病気を防ぐ第一歩を踏み出しましょう。

女性の健康にかかわる女性ホルモンついて
「知識がない」と回答した女性が両年代ともに全体の7割にものぼりました。
女性ホルモンに関して知っていることを聞いてみると、
月経・PMSに関する知識は35~59歳よりも20~34歳の方が高く、妊娠のしくみについては同等。
その他の知識に関しては、全般的に35~59歳の方が高く、
特に更年期症状・障害に関する知識は3倍もの差があることがわかりました。
2022年46.9% → 2024年39.5%[-7.3%]
2022年43.0% → 2024年39.2%[-3.8%]
20~34歳では妊娠のしくみについての知識、35~59歳では月経のしくみについての知識が減少していました。
女性ホルモンのための対処・対応は、両年代ともに食事・睡眠・運動といった健康三原則が上位を占めつつ、
20~34歳は運動、35~59歳は食事・睡眠での対処・対応が高くなりました。
また、特徴的なのは、20~34歳は、アプリや体温測定で、女性ホルモンの変化を把握していることに加え、
ピルやホルモン補充療法、医薬品・漢方を活用するといった、対処・対応において選択肢の幅が多いという点です。
2022年18.8% → 2024年23.9%[+5.1%]
2022年20.0% → 2024年23.7%[+3.6%]
2022年54.9% → 2024年50.2%[-4.8%]
2022年29.4% → 2024年25.7%[-3.6%]
2022年16.7% → 2024年19.3%[+2.6%]
両年代において、「医療機関で処方された医薬品・漢方薬を活用する」が増加。
さらに20~34歳においては、「ピルやホルモン補充療法を活用する」も増加する一方、「栄養バランスの良い食事を摂る」、「アプリや体温測定によって、自分の女性ホルモンの変化を把握している」という回答は減少しました。
女性ホルモン「エストロゲン」は、女性の守り神として、さまざまな恩恵を与えてくれる一方で、
その変動によって、女性特有の不調が起こりやすくなります。
女性ホルモンに関する正しい知識を身に付け、日頃からの生活習慣を見直しましょう。

女性の周囲環境に関して、20~34歳では5割以上、35~59歳では6割以上と、
多くの女性が女性の周囲環境は、女性の健康に知識・理解がないと感じているようです。
両年代ともに半数以上が 「女性の健康」に関して、家族やパートナーの理解があると感じており、
その傾向は20~34歳の方が高くなる結果となりました。
一方、企業における「女性の健康」のための取り組みは、両年代ともに3割程度にとどまりました。
2022年22.9% → 2024年25.9%[+3.0%]
両年代で大きな変化が見られない中、
唯一35~59歳において、企業は女性の健康のために取り組みを行っていると感じる人が増加しました。
女性が働く職場に必要だと思う取り組みは、両年代で傾向は同じものの
20~34歳の方が全体的に高くなり、「産業医に婦人科の医師がいる」という回答のみ同等となりました。
2022年40.3% → 2024年36.3%[-4.0%]
2022年53.1% → 2024年46.8%[-6.3%]
2022年45.0% → 2024年39.9%[-5.0%]
2022年29.8% → 2024年26.2%[-3.6%]
2022年42.2% → 2024年36.8%[-5.4%]
2022年18.7% → 2024年15.8%[-2.9%]
2022年24.1% → 2024年21.9%[-2.2%]
2022年21.9% → 2024年19.3%[-2.6%]
「託児所の設置やベビーシッターの利用支援制度がある」、「妊娠や育児期に女性が働き続けやすい環境を整備している」という回答は両年代で共通して減少。さらに35~59歳では、「不妊治療の支援をしている」や、「産業医に婦人科医がいる」など、企業に求める様々な取り組みが減少していました。
企業における女性が働く職場について、両年代共に、
様々な取り組みが必要であると感じている一方、実際の状況は大きな差があるようです。
2022年の健康経営銘柄および健康経営優良法人の認定要件では、
「女性の健康保持・増進に向けた取り組み」が評価項目として明記されるほど、
社会において「女性の健康」への関心が高まっており、
企業の女性活躍を支える対応が期待されています。

生活への満足度を、自身での対処、医療機関の利用を両方している人と
両方していない人で比べてみると、両年代において、自身での対処も医療機関の利用も共に行っている人の方が
生活への満足における全項目において高いという結果となりました。
女性特有の健康課題に適切に取り組むには、
「女性ホルモン」に関する知識を習得し、自身の身体について正しく知ることが大切です。
そして、「女性ホルモン」への対処・対策として、一般的なセルフケアに加え、
医療機関も合わせて利用することでの健康状態の正しい把握と管理が、
生活満足度の向上につながります。
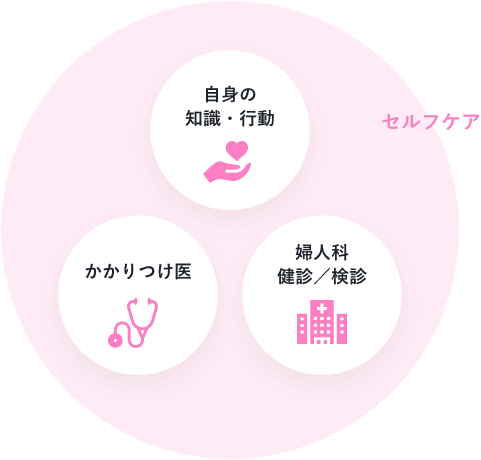
PMS・更年期症状は、
いずれも女性ホルモン(エストロゲン)が深く関わっています。
これらの諸症状とうまく付きあっていくには、
正しい知識の習得や「一般的なセルフケア」に加えて、
医療機関を利用し、自身の健康状態を把握して対処すること
が大切です。
大塚製薬の「女性の健康推進プロジェクト」は、
女性のヘルスリテラシーを向上すべく、
Webサイト・セミナー等を通じた情報発信などに
取り組んでいます。



2025/10/10
女性のヘルスリテラシー調査|2025年版
日々の生活に対する満足度に影響大!もっと輝きたい女性が取り組むべきヘルスケアとは?



2022/02/24
働く女性の健康意識調査
女性自身と企業に知って欲しい
昇進辞退、そして退職も…
「PMS・更年期症状」が仕事に及ぼす影響とは?