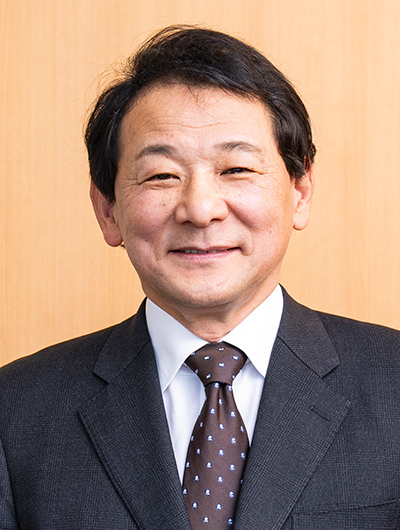「雨が降ると頭痛がする」「気分が落ち込む」など、天気によって不調をきたす人は多く、「天気痛」がある人は、国内推計1,000万人以上と言われています。「天気痛」の原因やメカニズム、緩和する対策などについて、天気痛ドクターで知られる愛知医科大学客員教授の佐藤純先生にお話を伺います。
気象好きな少年が天気痛ドクターに
ー 医師を目指し「天気痛」ついて研究されるようになったきっかけを教えてください。
もともと、星や雲に興味があり、空を眺めている少年で、宇宙に行きたいと思っていました。外科医だった父の影響で医師を目指しましたが、興味は別にあり、名古屋大学の環境医学研究所で研究者の道を歩むことになったのです。

痛みを研究のテーマにしたのは、大学院の指導教員が自律神経と痛みの専門だったことがきっかけです。その流れで、アメリカのノースカロライナ大学に留学し、慢性疼痛と自律神経に精通している方のもとで、最先端の研究をする機会を得ました。そこで、私は交感神経と痛みの神経との異常なカップリングを発見し、医学雑誌「サイエンス」に掲載されて話題になったことは、やりがいにつながりました。

帰国後、研究を深め、その成果を治療に活かすためにも臨床が必要だと考え、名古屋市立大学病院で、慢性痛の患者さんの外来を担当させていただきました。そこで気になったのが、「天気が悪くなると頭痛がする」「調子が崩れる」と訴える患者さんが多いことでした。当時、こうした現象は「気のせいだ」で済まされていましたが、私はとても不思議だったのです。
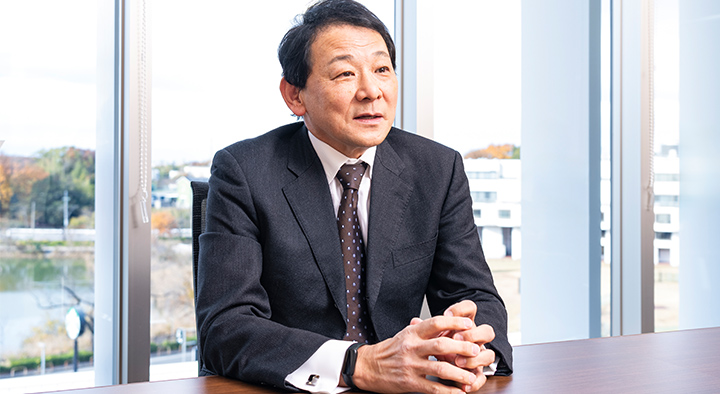
そんなとき、あるテレビ番組のディレクターから依頼があり、「雨が降ると古傷が痛むのは本当か」というテーマで実験を行うことになりました。チャンバー(密閉式タンク)に被験者が入り、チャンバー内の湿度や気圧を上下したところ、顕著な結果が出たのです。しかし、ディレクターに「なぜ、このような変化が起こるのか」と質問されても、私は答えることができませんでした。
この出来事がきっかけになり、どのようなメカニズムで気象が体調に影響を及ぼすのか、「天気と痛みの関係を科学的に解明しよう」と決意し、本格的に研究に乗り出したのです。
天気痛とは何か。その原因とメカニズムについて
ー 天気痛とは具体的にどのようなものでしょうか。
「天気痛」とは病名ではなく、天気や季節の変化で不調をきたす病態の総称で、私が名付けました。慢性痛には思い込みなどの心理的な影響がありますから、患者さんには、「痛み日記」を渡し、天気や痛み、運動や睡眠などを記録していただき、症状の天気依存性を客観的に評価して治療を進めます。

天気痛の潜在患者数は、全国で少なくとも1,000万人以上いると考えられます。症状としては、片頭痛、だるさ、めまい、耳鳴り、肩こり、古傷が痛む、腰痛、膝の痛み、喘息などの悪化、うつ(気分の落ち込み)など人それぞれですし、レベルも異なります。天気痛の症状として最も多いのが頭痛ですね。頭痛はQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質)を下げるので、悩まれている患者さんは多いのです。
天気痛には男女差があり、女性が男性の3~4倍も多い傾向があります。女性は首が細い、筋肉量が少ない、冷えやすいなどの要因があると思いますし、もしかしたら、女性のほうが自然への感受性が敏感なのかもしれません。
天気痛には男女差があり、女性が男性の3~4倍も多い傾向があります。女性は首が細い、筋肉量が少ない、冷えやすいなどの要因があると思いますし、もしかしたら、女性のほうが自然への感受性が敏感なのかもしれません。
ー 天気痛の症状が出る原因は何でしょうか?
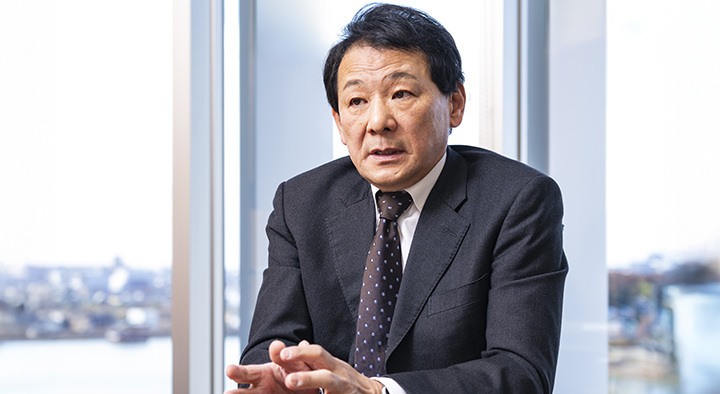
人の体への影響の点から考えるとき、天気には「気温・気圧・湿度」という3つの要素があります。気温や湿度を感じるセンサーは皮膚や粘膜などにあり、「寒い」「湿っぽい」といった気温や湿度の変化は、皆さん感じやすい。一方、気圧の変化は日常では気づきにくいですよね。
しかも、気圧の変化を感じるセンサーはどこにあるのか、これまで誰も研究していませんでした。
晴れたり雨が降ったり、風が吹いたりといった気象は気圧の変化が大きく関わっています。実際、天気痛の症状がある人は、天気の崩れや回復など、気圧が変化するときに症状が出やすいんですね。
では、気圧の変化を感じるセンサーはどこにあるのか。名古屋大学の学生たちの協力を得て研究を続けた結果、見えてきたのが「内耳」でした。内耳は耳の奥にある器官で、平衡感覚をつかさどる三半規管や前庭と聴覚をつかさどる蝸牛(かぎゅう)からなります。
では、気圧の変化を感じるセンサーはどこにあるのか。名古屋大学の学生たちの協力を得て研究を続けた結果、見えてきたのが「内耳」でした。内耳は耳の奥にある器官で、平衡感覚をつかさどる三半規管や前庭と聴覚をつかさどる蝸牛(かぎゅう)からなります。
天気痛のメカニズムについて、私は2つのルートがあると考えています。
1つは、気圧の変化を内耳が感じ取ると、前庭神経を介して、その情報が脳に伝えられ、その変化(ストレス)によって、自律神経のアンバランスを引き起こすというものです。

天気痛のメカニズムについて、私は2つのルートがあると考えています。
1つは、気圧の変化を内耳が感じ取ると、前庭神経を介して、その情報が脳に伝えられ、その変化(ストレス)によって、自律神経のアンバランスを引き起こすというものです。自律神経とは生命を維持するために、自分の意思とは無関係に身体の機能を自動調節する神経で、交感神経(活動しているときに優位になる)と副交感神経(リラックスしているときに優位になる)からなっています。
自律神経とは生命を維持するために、自分の意思とは無関係に身体の機能を自動調節する神経で、交感神経(活動しているときに優位になる)と副交感神経(リラックスしているときに優位になる)からなっています。
交感神経が優位になると、血管が収縮して、痛み物質が生じ、痛みの神経が刺激されて、頭に慢性的な痛みが出ると考えられます。また、倦怠感や肩こりなども自律神経の乱れが関係していると思われます。
交感神経が優位になると、血管が収縮して、痛み物質が生じ、痛みの神経が刺激されて、頭に慢性的な痛みが出ると考えられます。また、倦怠感や肩こりなども自律神経の乱れが関係していると思われます。
もう1つは、交感神経が痛みの神経に直接作用するルートです。通常、交感神経が痛みの神経に直接作用することはありませんが、片頭痛や慢性痛がある場合、交感神経と痛みの神経に連絡が生じるケースがあるのです。
ー 天気痛の症状がある人とない人とではどのような違いがあるのでしょうか。

天気痛の症状がある人は、内耳の感受性が高く、気圧の変化によるストレスが大きいことが考えられます。
天気痛を引き起こす気圧の変化は、台風のときのように大きいとは限りません。例えば、1日のうちでも、気温が上がり下がりすることで、周期的な気圧の変化が生じています。実際、朝の9時と夜の21時は気圧が高く、15時頃は低いのですが、この変動が大きいほど、天気痛を引き起こしやすくなります。
また、低気圧が発生するとき、わずかな気圧の振動が起こります。このわずかな微気圧変動でも、内耳が敏感な人にとっては影響があり、気圧が下がる数日前に天気痛が起きることもあるのです。
では、気圧の変化を感じるのは「内耳」だけかというと、そうとは限りません。天気痛には、まだまだ解明されていないことがたくさんあります。環境は病気の原因にもなるし、健康のきっかけにもなる。環境を無視したらいけないんです。だからこそ、解明できたら面白いし、追究し続けていきたいと思っています。
この記事をシェアする