補食選択のポイント
私たちの健康を支える基本は1日3食の食事ですが、忙しい毎日の中で理想的な食事タイミングを維持するのは難しいものです。仕事で夕食が遅くなったり、家事や育児に追われて落ち着いて食事ができないこともあるでしょう。そんなとき、不足しがちな栄養素やエネルギーは「補食」で効果的に補うことができます。
補食で栄養バランスを整える
「補食」とは、不足する栄養素や成分を補うために摂取する食事のことです。例えば、十分なたんぱく質が摂れていない場合は、ヨーグルトやサラダチキンなどが補食としておすすめです。また、スポーツ活動や体力を使う仕事など、1日の活動量が多い場合は、適切なタイミングでの補食がパフォーマンスの維持や疲労回復をサポートするというメリットをもたらします。
「おやつ」との最も大きな違いは、「必要な栄養素」を意識的に補っている点にあります。一般的におやつは、主にエネルギー補給と心の満足感を得るための甘いお菓子やスナック類を指します。美味しいおやつで気分転換やリラックスすることも心の健康には欠かせませんが、カロリー過多や栄養バランスの偏りに注意しながら選ぶことが大切です。
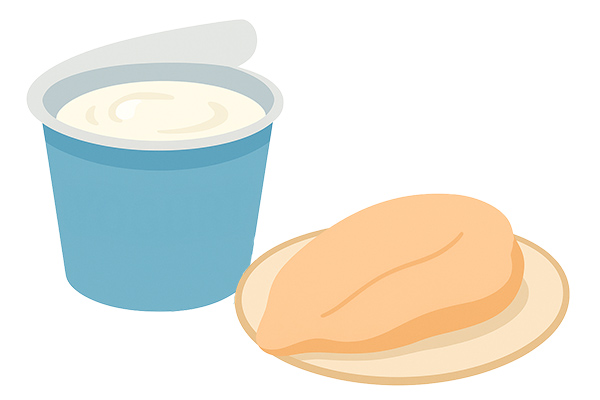
「おやつ」との最も大きな違いは、「必要な栄養素」を意識的に補っている点にあります。一般的におやつは、主にエネルギー補給と心の満足感を得るための甘いお菓子やスナック類を指します。美味しいおやつで気分転換やリラックスすることも心の健康には欠かせませんが、カロリー過多や栄養バランスの偏りに注意しながら選ぶことが大切です。
補食で補いたい栄養素
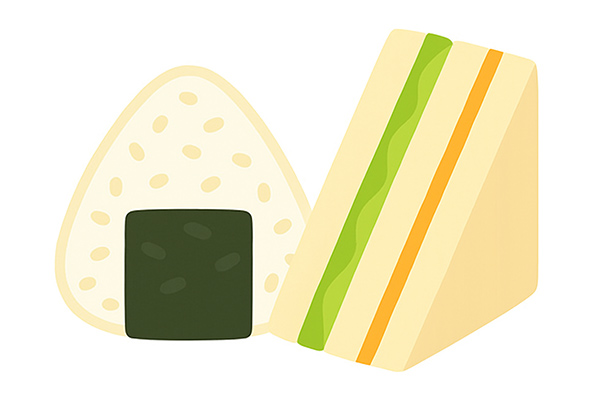
補食は1日あたり約200kcalを目安にするとよいでしょう。これは中程度のおにぎり1個や小さなサンドイッチ程度のカロリーであり、次の食事の妨げにならない適度な量です。
「朝食の時間がない」「出先で昼食をとる場所がない」という現代人によくある状況では、必要な栄養素がバランスよく含まれている栄養補助食品を活用するのも賢明な選択肢です。これらの製品は携帯しやすく、どこでも手軽に摂取できるため、忙しいライフスタイルに合わせて上手に活用しましょう。さらに、保存性も高いため、災害時の非常食としても役立ちます。
「朝食の時間がない」「出先で昼食をとる場所がない」という現代人によくある状況では、必要な栄養素がバランスよく含まれている栄養補助食品を活用するのも賢明な選択肢です。これらの製品は携帯しやすく、どこでも手軽に摂取できるため、忙しいライフスタイルに合わせて上手に活用しましょう。さらに、保存性も高いため、災害時の非常食としても役立ちます。
1. 炭水化物(糖質)
炭水化物は、カラダを動かすエネルギー源となる栄養素です。体内でブドウ糖(グルコース)に分解され、筋肉や肝臓に筋グリコーゲンとして蓄えられます。主に、運動時のエネルギー源として利用されます。
また、炭水化物は、脳のエネルギー源にもなります。ブドウ糖は、眠っている間も消費されるため、朝起きたときは脳も空腹状態になっています。そのため朝食を抜くと脳のエネルギーが不足し、集中力の低下や判断力の鈍化につながります。よい1日のスタートを切るためには、炭水化物をはじめとしたバランスの良い朝食の摂取が大切です。
代表的な補食としておにぎりが挙げられますが、選び方にも工夫が必要です。脂質の高い具材が入ったものよりも、疲労感軽減に役立つ梅干しや、不足しがちなたんぱく質を補える鮭などがおすすめです。また、全粒粉のパンやクラッカーも良い選択肢です。
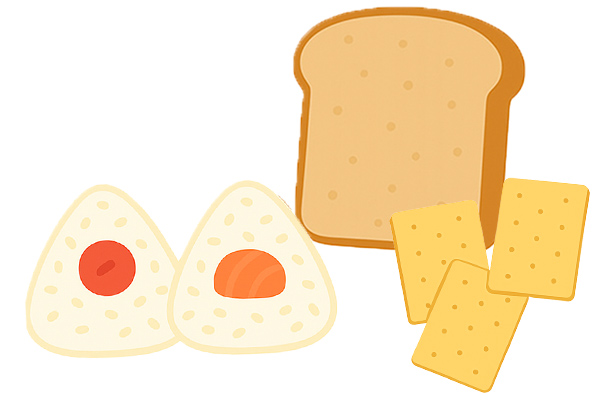
2. ビタミン、ミネラル
食事で摂った栄養素は「代謝」によって、消化吸収の過程でエネルギーになったり、カラダをつくる材料になったりします。その代謝がスムーズに行われるためには、ビタミンやミネラルが不可欠です。
また、疲労軽減や免疫機能の維持に欠かせない栄養素でもあります。バナナやリンゴなどの果物、ドライフルーツであれば、これらの栄養素を手軽に摂取することができます。特にバナナはカリウムが豊富で、筋肉の働きをサポートしたり、疲労感の軽減に役立ちます。ナッツ類も良質な脂質とミネラルの供給源として優れています。
ビタミン・ミネラルはサプリメントからも補うことができますが、あくまでも「補助」として活用し、できるだけ実際の食物から栄養素を摂取することを心がけましょう。食物に含まれる栄養素は単体ではなく複合的に作用することで、より高い健康効果をもたらします。
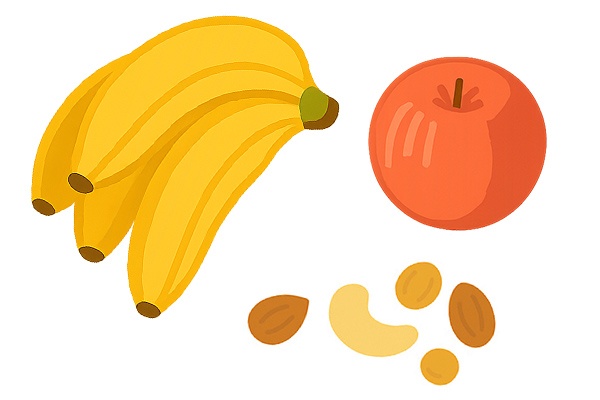
ビタミン・ミネラルはサプリメントからも補うことができますが、あくまでも「補助」として活用し、できるだけ実際の食物から栄養素を摂取することを心がけましょう。食物に含まれる栄養素は単体ではなく複合的に作用することで、より高い健康効果をもたらします。
3. たんぱく質
たんぱく質は、カラダを作る材料として必要な栄養素です。食事から摂取したたんぱく質がアミノ酸に分解されてカラダに吸収されると、筋肉や臓器、肌、髪、爪などの材料として使われるほか、ホルモンや免疫物質などになり、さまざまな働きをしています。また、たんぱく質が不足すると、筋肉量や疲労感だけでなく、集中力やモチベーションなどにも影響を与えることがあります。特に高齢者や運動をする人は、意識的にたんぱく質を補うことが重要です。補食としては、サラダチキンや無糖のヨーグルト、ゆで卵、チーズなどを選ぶと良いでしょう。植物性たんぱく質源として、大豆製品や豆類も優れた選択肢です。
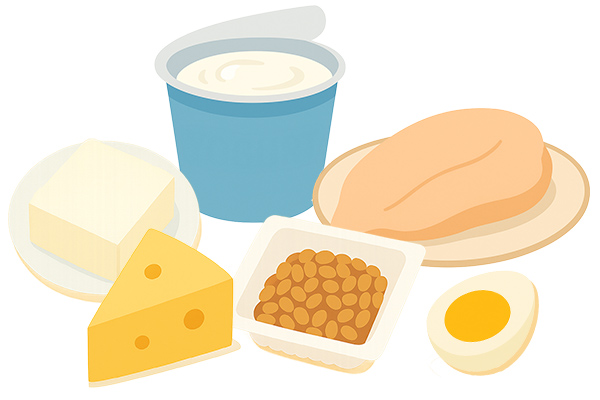
空腹時間が長くなるときは、低GI食品を活用
仕事などで夕食が遅い時間になってしまうと、空腹による集中力の低下や、その反動としての食べ過ぎなどの悪循環に陥りやすくなります。このような場合の補食には、低GI食品の活用がおすすめです。
GI(グリセミック・インデックス)とは、食品に含まれる糖質が体内でどれくらいの速さで吸収されるかを示す指標です。糖質の吸収速度が速いものを高GI食品、糖質の吸収が穏やかなものを低GI食品と呼びます。
糖質を多く摂取すると血糖値が上昇し、膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンは血液中のブドウ糖を細胞内に取り込むよう促すため、血糖値を下げる働きがあります。また、インスリンには脂肪の合成を高めて分解を抑制する作用もあるため、糖質の摂り過ぎは過剰なインスリン分泌を促してメタボリックシンドロームの一因となります。

さらに、急激に上昇した血糖値は、その後急激に下がることがあり、血糖値の変動が大きくなることがあります。これを『血糖値スパイク』と呼び、これにより、食後に眠気や、空腹時にふらつきを感じることもあります。
高GI食品は血糖値を一気に上昇させて多量のインスリンを分泌させる一方、低GI食品は血糖値の上昇がゆるやかなため、インスリンもゆっくりと分泌されるというメリットがあります。低GI食品としては、玄米やそば、りんご、無糖ヨーグルト、キノコ類やピーマンなどの野菜が挙げられます。

特に注目したいのは大豆などの繊維質が豊富なマメ科植物です。これらは低GIであるだけでなく、次の食事でも血糖値の上昇を抑える「セカンドミール効果」という優れた特性を持っています。混ぜご飯や雑穀米なども、白米よりもGI値が低く、持続的なエネルギー供給源として優れています。
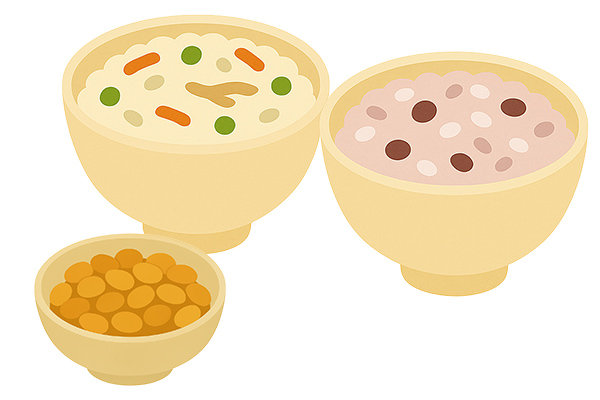
適切な補食選びは、単に空腹を満たすだけでなく、健康的な食生活の重要な一部となります。日々の生活習慣や活動量に合わせて、自分に必要な栄養素を意識的に補うことで、バランスの取れた健康的な食生活を実現しましょう。
この記事をシェアする