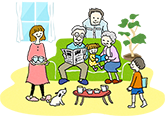結核は世界の問題
アジアやアフリカなどの発展途上国で特に患者さんが多いのです
世界の結核は?
年間1080万人が新規に結核を発病し、125万人が亡くなっています(2023年、WHO推定)(表・図12)※。これらの指標は、今世紀に入ってから緩やかな下降傾向にありましたが、新型コロナウィルス感染症の流行のために2020年には死亡率が、2021年には罹患率がそれぞれ上昇傾向に転じました。患者さんが多いのは発展途上国です。結核はなかなか減らない病気で「再興感染症」とよばれています。とくに最近は「HIV感染合併結核」「多剤耐性結核」など、質的にも難しい問題が浮上しています。
- ※HIV合併結核による死亡があり、世界では16万人に達します。
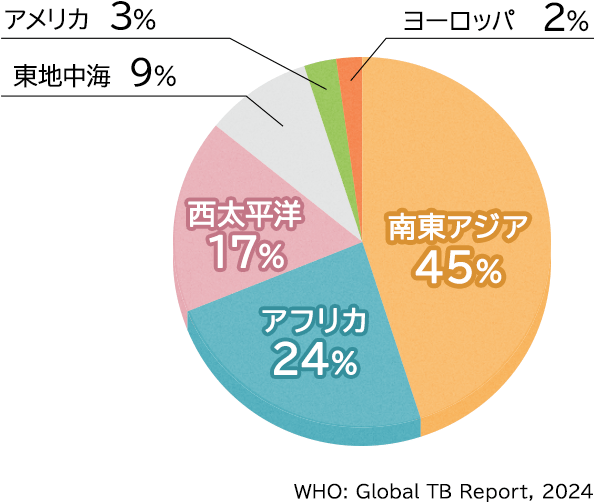
表 世界の結核負担(患者・死亡発生件数、WHO推定 2023年)
| 発生患者数(千人) | 死亡者数(千人)※ | 患者中HIV陽性率% | |
|---|---|---|---|
| 南西アジア | 4,910 | 606 | 2 |
| アフリカ | 2,550 | 403 | 18 |
| 西太平洋 | 1,880 | 94.9 | 1.3 |
| 東地中海 | 936 | 86.2 | 0.5 |
| アメリカ | 342 | 35 | 12.2 |
| ヨーロッパ | 225 | 22.5 | 12.9 |
| 世界 | 10,800 | 1,251 | 6.1 |
- ※HIV感染者の死亡16万人を含む
WHO: Global TB Report 2024
世界の結核に対する取り組みはどうなっているの?
世界の結核対策「結核終息戦略」
WHOは1993年「結核緊急事態宣言」に続いて、1994年DOTS戦略を発表し、結核治療の強化を中心とした新しい結核対策に取り組み始めました。この戦略は、それまでの結核治療の失敗の原因であった患者の治療脱落に対し、「規則的な服薬の継続」を患者まかせにせず、毎日患者の服薬を医療職員が見届ける、というもので、まずアフリカ、中米のいくつかの国でいい成績を収め、やがて米国のような低まん延国も含めて世界中に広まっていきました。日本も2001年から、「日本版DOTS」として導入され、普及し、やがて法令で規定される治療方式の一部分となります。
DOTS(Directly Observed Treatment, Short Course、直接観察短期化学療法)の成功をうけて、結核対策は歩留まりの大きい途上国支援、ということで結核問題や結核対策の世界の注目が集まり、さまざまな支援組織が稼働し始めました。
勢いづく世界の結核対策運動とコロナの挑戦
- WHOが中心になって、結核対策に関連する政府・民間の機関や団体が大同団結した「ストップ結核パートナーシップ」が、立ち上げられ、アドボカシー(普及啓発)を中心に主として途上国の結核対策推進のサポーターとなりました。ここには「世界抗結核薬基金」(Global Drug Facility)があり、途上国の求めに応じて、よいDOTS実施のための良質な抗結核薬をはじめ、診断機器を無償で提供しています。
- 2000年の九州・沖縄G8サミットでの日本の提唱をきっかけに、感染症が途上国の開発の障害になっているとの認識をもとに、国連の主導で「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」が発足、ここに世界三大感染症の対策への強力な資金提供の組織が立ち上げられました。資金は米国をはじめ先進国や民間機関が拠出しています。
- 2018年、結核対策に対する世界各国の政治的な関与を強化するため、国連が各国の首脳を集めて協議をし、「2030年までに結核をなくす」ための努力をするという宣言を出しました。
- 21世紀に入ってからWHOは結核対策を国連の「ミレニアム開発目標」(MDGs)に合わせて推進してきましたが、国連が2015年にMDGsから「持続可能な開発目標」(SDGs)に目標を引き上げるのに協調して、結核対策を結核終息戦略に発展的に転換しました。この戦略では、2035年までに「世界の結核を事実上終息させる」(実際的には罹患率を人口十万対10以下に)ことを目標に、そのための中間目標や必要なプロセスを具体的に提案しています。
- そんな矢先に2019年に始まる新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、結核対策を非常にかく乱し(対策人員、資機材の占拠、人流の抑制による医療の圧迫など)、結核死亡や発生の逆転上昇を招く結果となっており、「結核終息戦略」への新たな挑戦が加わることとなりました。
残された結核対策の課題
多剤耐性結核とは?
結核菌は、結核の治療薬に対して抵抗性がついてしまい、薬が効かなくなってしまうことがあります(耐性化)。とくに手ごわいのが現在の結核治療の中でもっとも重要なイソニアジドとリファンピシンという2つの薬剤に同時に耐性となってしまう「多剤耐性結核」です。世界的に見て、最近この多剤耐性結核が増加しており、結核の増加を考える上で、現在もっとも深刻な問題になっています。日本でも決して油断はできません(図13)。図13には、最もよく用いられる一次抗結核薬の少なくとも一剤に耐性(図13「何らかの」耐性)頻度も示してあります。
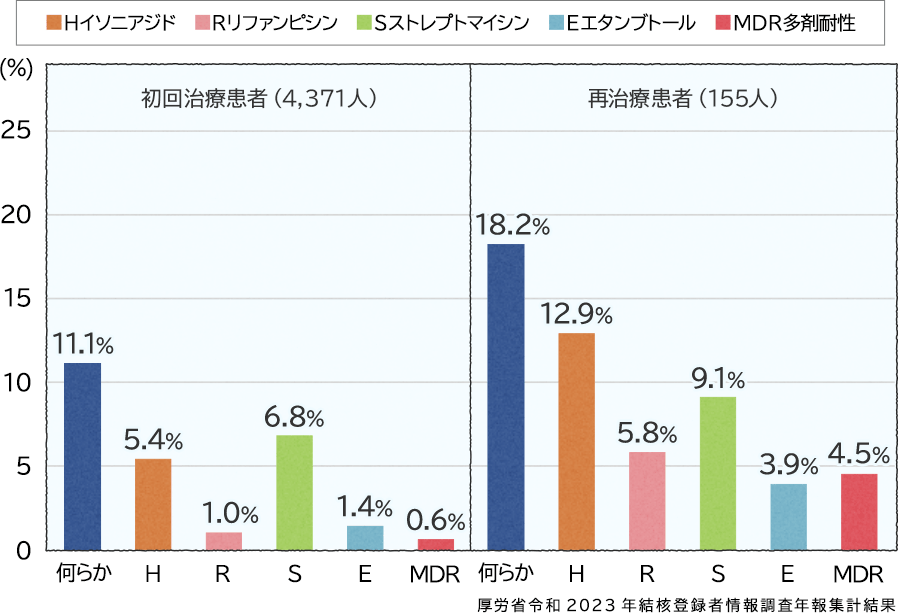
多剤耐性結核が生まれる背景としては、十分な効果のある薬の組み合わせによる治療が受けられない場合(信頼性のある薬剤感受性検査が行われなかった場合もあります)、または、薬剤の服用が不規則であったり、途中で中断してしまったりすることが挙げられます。治療を終え、結核が治ったようにみえても約2~5%の患者さんで再発が起こります※。図13の右側(再治療患者)はそのような患者さんでは薬剤耐性になっていることが多いことが示されています。一方、不幸にも耐性結核の患者さんから感染を受けて発病した人は最初から薬剤耐性です(初回治療患者、図13左側)。
- ※Chang, KC. et al.:Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 174, 1153-1158, 2006
薬剤耐性患者さんの治療経過
主軸の薬であるリファンピシンとイソニアジド(ヒドラジド)に同時に効かなくなると(多剤耐性)、結核の治療はとても困難になります。
治療には副作用の強い薬を何種類も、長期にわたって使わなければなりません。場合によっては手術が必要なこともあります。
それでも成績はあまりよくなく、日本でもごく最近まで、治癒が確認されたのは50~60%程度で※、残りの多くは死亡するか菌が止まらないままでした。
- ※吉山崇ほか:結核, 92, 529-534, 2017
多剤耐性結核治療の新薬の開発・導入
日本では新たに発生する結核患者のうち多剤耐性の人は全体の0.6%程度ですが、世界的には10%以上にもなる国が少なくありません。2023年の推定MDR/RR患者発生の割合は初回治療患者で3.2%、既治療患者で16%でした。国別の分布では、インド29%、ロシア7.4%、インドネシア7.4%、中国7.3%、フィリピン7.2%等となっています※。これの対策として有効な薬剤の出現が望まれていましたが、最近相次いで強力な新薬が導入され、効果が期待されています。ただし、これらの新薬に対する耐性が作られないように、DOTSの厳格な適用を含む正しい使用法とそれを支えるための技術の開発(薬剤耐性検査法、早期診断技術等々)がさらに望まれるところです。
- ※WHO: Global TB Report 2024